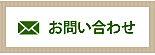スタッフブログ
スタッフブログ
ならさん家のお庭~デッキ選び~
2025-03-28
こんにちは、ならです!
実はうちの庭にデッキを付けようと思ってまして、、
デッキを付けることで室内とつなげてリビング空間を広く感じさせたり、屋外で遊ぶときに腰かけたりして使うことができるので、小さなお子様やペットがいるご家庭で特に採用されることの多い設備です。
ご存じの方も多いと思うのですが、大きく分けてタイルデッキとウッドデッキの2種類あります。
「タイルデッキとウッドデッキ、どっちも良さそうで決められない!」
という悩みはよく耳にします。
簡潔に結論を言えば、
「コスパならウッドデッキ」
「耐久性ならタイルデッキ」
がおすすめですが、選ぶ基準は他にもたくさんありますよね。
そこで今回は、それぞれの短所と長所を詳しく比較していきます。
タイルデッキ
◎メリット
・耐久性が高い
タイルデッキの耐用年数は「半永久」と言われており、約20年で交換が必要なウッドデッキに比べて大幅に長持ちするので長い目で見るとお得です。
・メンテナンスがしやすい
ホースや高圧洗浄機を使用し水で流せば大抵の汚れが落ちますので、メンテナンス性にも優れ、忙しい共働き世帯に人気です。
・バリエーションが多い
職人さんの手でタイルを貼り付けていくので、様々なカラーを使ったりランダムに貼るなどのオリジナル性を出せます。
▲デメリット
・価格が高い
同じ面積で工事した場合、タイルデッキはウッドデッキより高額になってしまいます。
・滑りやすい
ウッドデッキに比べると雨や雪が降ったときに滑りやすく、転倒したときにタイルが硬いためケガするリスクもあります。
・夏場は高温になりやすい
日光の照り返しが強いことも特徴であり、夏場はかなりの高温になってしまいます。
・段差がある
外壁の劣化を防ぐため、フローリングの高さより10〜15cmほど下に施工するのが一般的ですので、段差が気になる方には不向きです。
ウッドデッキ
◎メリット
・価格が安い
タイルデッキより格安で施工でき、工事日数も1日あればほぼ完成する手軽さが魅力です。
高さのある場所にタイルデッキを作るとかなりの高額になるため、斜面に設置するならウッドデッキが適しています。
・木の温かみがある
独特の木の風合いと温かみ、ナチュラルなデザイン性は、天然木だけが持つメリットです。
タイルデッキほど照り返しで熱くならないため、夏場に家族で過ごしやすいという特徴もあります。
・室内との一体感が出やすい
ウッドデッキは室内の床面とフラットの高さで施工ができるので、窓を開けるとリビングとつながって見えますよ。
▲デメリット
・劣化が早くメンテナンスが大変
日光や雨風で劣化するスピードが速く、汚れが付きやすいという特徴があります。
雨などが降ってウッドデッキが濡れると、ヌメリやカビが発生することもあります。
また、ウッドデッキは地面との間に空間があるので、そこから雑草が生えたり、落ち葉が溜まったり、クモの巣ができる可能性も高いです。
そういった点では、タイルデッキよりもウッドデッキの方が手入れに手間がかかります
・反りやささくれができてしまう
天然木はどうしても反りやささくれができてしまうため、転倒や怪我の危険性もあります。
耐久性の高い「人工木」のウッドデッキもありますが、BBQで火の粉が落ちると溶けてしまう難点も悩ましいですね。
メンテナンス性に優れ、長持ちするタイルデッキと、コスパに優れ、ナチュラル感が魅力のウッドデッキ。
どちらが良いかは、何を重視しているかによって大きく変わります。
高橋造園でもデザイン性だけではなく、日々の使い勝手やデッキの素材の選び方まで、プロならではの観点でアドバイスさせていただきます
ならさん家はどちらを採用するのでしょうか、、!!
それではまた~
防犯対策
2025-03-21
関東を中心に全国で被害が相次いでいる強盗・窃盗事件のニュースを見ない日はないのではないかと思うくらい多いですが、今回は外構で防げる対策をご紹介できたらなと思います。
犯罪者が嫌う4原則「音・光・時間・人の目」この4つから外構でできる事を考えると
「音」…家の周りに砂利を敷く。
「光」…夜間に敷地内を照らすような照明やセンサーライトの設置。
「時間」…侵入に時間がかかるようにカーゲートやチェーンポールを置く。※置くだけの物だとホームセンターでも安く入手できます。
「人の目」…犯行を諦める1番の理由になるそうです。
イルミネーションを付ける、庭や玄関、駐車場に花や植物を飾る(植える)と近所の人や通行人の目が集まるので、ガラスを割ろうとはならないそうです。
他にもインターホンやポストが玄関付近にあると、侵入者を玄関先まで誘導する事になるので、できるだけ玄関から離れた門扉や門柱に設置するとよいとされています。
又、カーポートやテラスの屋根・物置等、2階のバルコニーへの足場になるので、設置場所には注意が必要です。
そしてゴミが散乱し、庭の手入れが不十分な家は狙われやすいそうです。
お家の場所や生活スタイルによって出来る防犯対策は変わってきます。
1つでも外構で取り入れられるものがあれば対策してみてください。
鈴木
土間コンクリート VS アスファルト 家の駐車場はどっちがいい!?
2025-03-14
こんにちは!加藤です。
皆さんの家の駐車場は土間コンクリートでしょうか?
アスファルトでしょうか?
そもそも駐車場の素材なんて知らないっていう方もいらっしゃると
思いますので、特徴を簡単に説明しましょう!
■土間コンクリート舗装の特徴■
なめらかで平らな表面、グレー色をしているのがコンクリート舗装です。
砂や砂利、セメントや水を使って凝固させたもので、駐車場だけでなく、
アプローチやその他の外構のスペースにも使用されます。
耐久性があり、非常に硬いのが特徴ですが、柔軟性が無いため、
ワイヤーメッシュ等を中心に入れて補強する必要があります。
その分手間もかかります。
【メリット】
・非常に硬く、衝撃にも耐えられ、欠けやひび割れが起こりにくいという
メリットがあります。
・耐久性があるため、傷つくことが少なく、メンテナンス等の維持費が少なくてすみます。
・夏でも高温になりにくい。
【デメリット】
・初期費用が高い・・・(維持費がかからず長く使えるので長い目で見れば経済的です。)
・使用できるまで時間がかかる・・・施工後数日間は駐車場がつかえません。
・雨の日は滑りやすい・・・表面が平らで凹凸のない仕上げにすると、
見た目がきれいで掃除もしやすいですが、雨の日には滑りやすくなります。
より安全を重視するのであれば、刷毛引き仕上げにすると滑りにくくなります。
■アスファルト舗装の特徴■
ざらざらとした表面で黒褐色、道路や駐車場によく使われているのがアスファルト舗装です。
燃料をつくる際に残った残留物と骨材を混ぜたアスファルト合材を敷き詰めて転圧をすることで舗装します。
施工後、温度が50度以下になると車が通れるようになるため、
コンクリートよりも短い時間で使用できるようになります。
【メリット】
・施工後数時間で車を駐車場に入れることができます。
・排水性がよく、くぼみなどができていなければ水たまりはできにくいです。
【デメリット】
・耐久性が低い・・・素材が柔らかく、ひび割れやくぼみ、わだちができやすい
コンクリートに比べ、アスファルトは耐久性が低く、使っていける期間も短い
・維持費用が高くつく・・・ひび割れやくぼみ等ができやすいので、
その都度修繕する費用が必要になります。
・表面温度が高くなる・・・夏場の暑い時期には60度を超える時もあり、
やけどに注意が必要です。高温のアスファルトはやわらかくなってしまい、
ゆがんだまま冷えて固まる場合もある。
■家の駐車場にコンクリート舗装が選ばれる理由■
一般家庭の駐車場はほとんどコンクリート舗装ですよね。
選ばれる理由としては、長期的に考えた場合、アスファルトより費用がかからない。
きょうどがあり、耐久性もあるので、補修がほぼ必要ない。
見た目も現代の住宅にマッチします。
初期費用こそ大きく感じますが、長い目でみると
耐久性に劣るアスファルトより良い状態で使っていけるでしょう。
土間コンクリートもアスファルト舗装も施工可能です。
用途・イメージ等に合わせてご相談ください♪
それではまた~
オシロイバナ
2025-03-10
針生です!
最近、あるアニメを見てたら
その中に出てきた植物について勉強になったので、
つぶやかせていただきますね
皆さんこの植物、見たことありますか?
私も公園とかにありそーって何気なく思ったんですが、
実はこの植物、「オシロイバナ」といいます。
ん?って疑問に思った方いませんか?
私も思いました。
花びらがピンクなのにオシロイ?って…
実はこのオシロイバナ、種子の中から「おしろい」に似た白い粉が入っていることから
「オシロイバナ」と呼ばれるようになったそうです。
現代ではフェイスパウダーやファンデーションなどと言うので、
おしろいということから、昔から知られている植物なんだと感じました。
このオシロイバナ、実は花びらがピンク色以外にも赤・黄色・白・複色とあり、
夏~秋の時期の夕方に花を咲かせるため、別名:夕化粧とも呼ばれるそうです。
一発でこれはオシロイバナだ!って気づけませんね
オシロイバナは今は野生化してしまったんですが、
昔は観賞用で日本に渡来し栽培され、香りがよく様々な色の花を咲かせるため、
軒下などに植え、夕涼みを楽しんでいたそうです。
さて本題、こちらのオシロイバナ
実は毒を持っています
根・茎・種・葉・花、全てに毒性があり、特に根と種にはトリゴネリンと言った成分が入っており、
誤飲してしまうと、腹痛・嘔吐・下痢・皮膚の炎症といった症状が出ます。
現代は野生化してどこにでも生えいていますので、お子さんやペットが間違って触れたり誤飲しないよう注意が必要ですね。
拝見したアニメでは、堕胎剤にもなるそうです。恐ろしい…
ただ、調べると利尿作用や関節炎の生薬として処方されるとデータもあったので、
専門職に基づき、用法用量を守れば薬としても使える、
オシロイバナ以外の植物、全てがそう言い切れるのかなと私の中で見解になりました。
たった一つのアニメ作品から歴史や薬草について知ることができ、
また職業柄、様々な植物をみることから人と植物の繋がりはなくてはならないのだと、
改めて感じました。
長々と難しい話をしてしまったかと思いますが、
ここまで読んで下さり、ありがとうございます
これを機に興味ある方は色々な植物に目を向けてみてはいかがでしょうか?
ではまた~
適正配置
2025-02-28
こんにちは、ならです。
高橋造園ではこの時期になると社員全員分の健康診断の予約を取ります。
健康診断って実は法律で実施が定められる企業の義務って知っていましたか?
2024年4月より、建設業にも「時間外労働の上限規制」が適用されるようになりました。
過度の残業や長時間労働、休日が取れないといった過酷な労働環境が大きな社会問題となっており、従業員の健康状態の管理は、本人だけでなく、従業員を雇う会社にとっても重要な義務となっています。
そこで今回は、建設業界における“適正配置”のお話をさせていただきます。
建設工事の現場では、安全に効率よく作業を進めることが求められます。
作業の量や求められる質に対して、作業者の保有資格、経験や知識、技能や体力に応じて作業者の人選と人数を割り当て、最も適した作業者を配置することを「適正配置」といいます。
適正配置の進め方で重要なポイントはおおよそ以下の通りです。
・作業の期限
・全体の作業量と必要な人数の見極め
・個別の作業量と求められる作業品質
・作業者の技能レベル
・作業者の保有資格と作業に必要な資格
・共同作業の場合は組み合わせ(経験、年齢、体力、体格、性格、性別、相性など)
・作業者の要望
・作業者の体力と健康状態
・作業者の教育・育成につながる作業かどうか
高年齢作業者の適正配置
建設業では高年齢の作業者が多く、貴重な労働力です。
一方で年齢が高くなると体力や判断力、俊敏性などが衰え、労働災害による死亡者の割合は60歳以上が全体の3割以上を占めています。
令和2年には高年齢労働者の労働災害を防止する目的で「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(通称:エイジフレンドリーガイドライン)」が厚生労働省から公表されており、「危険な作業に就かせない」などの高年齢労働者への配慮が求められています。
若年作業者の適正配置
若年作業者は一般的に経験年数が短く、技能や知識、対応力などが未熟です。
そのため、労働災害における29歳以下の死傷者は他の世代に比べて非常に高い割合となっています。
経験の浅い若年作業者に対しては特に注意を払い、監督指導をこまめにおこなうなどの気配りの他、作業の事前説明も入念におこない、理解度を確認し、能力に応じた作業を割り振ります。
共同作業の場合は熟練作業者と組ませるなど、事故を未然に防ぐための配慮が適正配置につながります。
女性の適正配置
建設業における女性作業者の割合は極めて低く、全体の2パーセント程度とされています。
女性が少ない理由には体力の問題もありますが、トイレや更衣室など設備面で女性の受け入れ態勢が整っていないことがあげられます。
こうした現状に対して女性建設技能者から職場環境の整備を求める声があがっており、現場でも女性という前提に立った適正配置が求められます。
また、作業員の「健康状態」も適正配置措置に欠かせない情報です。
作業員名簿や新規入場者アンケートでも直近の健康診断の受診状況、最高血圧・最低血圧の記入が求められます。
重労働や野外作業が発生しやすい建設業において、意識障害を起こすことは大事故に繋がる可能性があるからです。
「最高血圧が○○以上の者は就業できない」といった明確な制限はありませんが、労働安全衛生法第65条の3にて、事業者は、労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならないという「安全配慮義務」があります。
適正配置通知を提出することによって、改めて作業員の健康状態を確認し、労働災害防止に努めていかなければなりませんね。
今回は適正配置のお話でしたが、健康は大事です!
私も腸活始めました!!
皆様も体調に気を付けて過ごしてくださいね