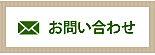スタッフブログ
スタッフブログ
寒肥について
2022-12-12
こんにちは、平井です。
仙台は最低気温が氷点下を下回る日が増えました。
立冬からひと月が経過し、寒さが本格的になってきましたね。
さて、以前のブログで冬季剪定について書きましたが、寒い冬の作業といえばもうひとつ重要なものがあります。
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、寒肥(かんごえ)と呼ばれる庭木に肥料をあげる作業です。
寒肥はその名の通り冬に与える肥料のことで、特に庭木にとっては肥料の中でも最も大切な物です。
春からの成長期に根・枝を伸ばし、花付きをよくするために重要となります。
多くの植物にとって冬は根の活動が最も低下し、外部からの影響を受けにくくなる休眠期になります。
これを利用して、土壌改良材や有機肥料を混ぜ根元から少し離れた周囲に穴を掘り肥料を埋め込みます。
地植えしている場合は、根が深くまで張っていることが多いので、土の表面に肥料を置いてもその成分が根に吸収されるには時間がかかります。
先述のとおり冬は根の活動が低下しているので、効率よく肥料を吸収するためには根が活動を始める春以降にどれだけ肥料を吸収できる状況化が大切です。
植物は春先に芽吹く前に根は活動を始めます。
冬に与えた肥料はゆっくりと分解され、春先以降に肥料として土に行きわたります。
そのため、春先に肥料の成分が根まで浸透することを想定して、肥料はその前の冬に与えるのが基本です。
そうする事でちょうど芽吹きの時期に肥料分が行き渡るという仕組みです。
庭木だけでなく、宿根草や多年草も花付きを良くし株を大きくするために効果的です。
地植えは一度の施肥でOKですが、鉢植えは土の量が限られているため、月に1度の割合で少量を2回に分けて施しましょう。
植物は上の図のように幹・枝と根の形が同じように広がって成長しています。
そのため枝先の下あたりに肥料を施すと効果的です。
寒肥を施す時はスコップで根の先端をざっくり切るつもりで溝や穴を掘って大丈夫です。
休眠期であればダメージは少なく、却って新しい根の発根が促される効果もあります。
寒肥には、有機肥料を使います。
有機肥料とは油かす、牛糞・鶏糞などの動植物本来の有機物を原材料とした肥料です。
土の中に埋め込んでしまえば、匂いも気になりませんし、虫がわくこともありません。
有機肥料に微生物が集まり、その微生物が時間をかけて春に向けて土を耕してくれます。
寒肥の季節は12~2月ですが、土が凍ってしまうような地域では、土が凍る前、もしくは溶けた後に施しましょう。
尚、春咲きの球根植物には、寒肥はやらず、芽が出てから肥料をあげてください。
芽が出る前に肥料をあげると、球根が腐ってしまうことがあります。
また、観葉植物や洋ランなど、寒いのが大嫌いな植物には寒肥は施しません。
これらの植物には、暖かくなってから生育期に肥料をあげてくださいね。
寒肥を面倒だと思われる方もいるかもしれませんが、前述したとおり寒肥は庭木肥料の中でも最も大切な物です。
手間をかけた分だけ、必ず植物は答えてくれます。
我が家の庭にも庭木がいくつかと宿根草が多く植えられているので、12月に入ってすぐに寒肥作業を行いました。
因みに我が家の寒肥は骨粉入りの油粕:7、腐葉土:1、バーク堆肥:1、もみ殻燻炭:1を混ぜこんだものを施肥しています。
尚、勘違いされている方も多いのですが、腐葉土とバーク堆肥は肥料ではありません。
これらは植物由来のため、肥料成分が含まれていますが、植物の生育に必要な量としては不十分です。
腐葉土とバーク堆肥、もみ殻燻炭には土の保肥性や保水性、通気性などを高め、土中の微生物の活動を活発にする作用があります。
つまり、土中の環境を良くする土壌改良材です。
もみ殻燻炭はアルカリ性ですので酸性土壌のpH矯正にも適しています。
肥料が家にない方や、肥料のブレンドがめんどくさい、という方は、ホームセンターで寒肥用肥料を購入すれば楽ですよ。
今まで一度も寒肥をしたことのなかった方は、今年の冬、是非一度お試しください。
ご自分でやる時間が取れない方や施肥の方法について心配のある方は、冬季剪定を含めてお庭のお手入れについて問い合わせフォームよりご相談ください。
庭木が豊かな春を迎えられるように、是非準備してみてください。
特にアジサイなどの花木は見違えるほどきれいに花を咲かせてくれること間違いなしですよ!