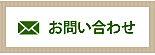施工ブログ
茶庭工事をご紹介します(*^^*)
2021-05-07
こんにちは!
今回は仙台市A様邸のお庭の工事をご紹介します。
今回の庭は、『茶庭』です。
茶庭とは、日本の庭の様式の1つで、茶事のための庭のことを言い、露地とも言います。
茶事に呼ばれた客人が茶室に入る前に通る茶庭は、
客人が非日常である茶事に入り込んでいくための装置の一つです。
では、茶庭をつくる際のポイントをいくつかご紹介しましょう(*^^*)
■蹲(つくばい)
客人が手を洗い、口をゆすぎ心身を清めて茶室に入るためのもので、
茶庭には欠かせない重要な要素です。
■中門(ちゅうもん)
庭全体を二つに仕切った「二重露地」で境界として使われています。
目隠しなどの役目はなく、四ツ目垣や枝折り戸などの簡素なものが使われることが多いです。
■飛石・延段(のべだん)
茶室へ向かうという露地の役割の中で、最も実用的な部分を担います。
延段は畳石ともいわれます。
飛石より安定感がありますが、延石ばかりだと固い印象になってしまうので、
飛石と取り混ぜて使うのが良いでしょう。
また、実用性のみをを優先すると美観が損なわれてしまうので、
バランスもとても大切です。
仙利休は実用性に6分・景観に4分の配慮をして石を打つよう推奨しているそうです!
■植栽
茶庭の植栽には基本的に決まりがありませんが、
四季を感じさせない植栽選びをしています。
ポイントは、茶室に入った時の”花一輪の美しさ”を際立たせる植栽です。
今回の工事でも常緑を植え、季節感を感じないよう工夫しています。
茶道には様々なきまりがあり、本格的な茶庭(露地)をつくるには知識が必要となります。
しかし、和の小庭を楽しむために、
茶庭(露地)を参考にする!という程度に考えて肩の力を抜いてもよいでしょう。
少し眺めるだけでも、和の景色があると心が和むものです(*'ω'*)
1・2枚目は施工途中の写真です。3枚目は完成写真です!
他にも完成写真が撮れましたら、施工例の写真にもUPしますので、お楽しみに‼
それでは、加藤でした(^^♪